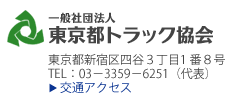交通安全・事故防止のために
トラックの追突事故多発
2003年6月から7月にかけて、高速道路で大型トラックによる追突事故が続発しました。とくに6月23日に愛知県新城市の東名高速上り線で起きた事故では、渋滞の最後尾に大型トラックがノーブレーキで追突し、12台を巻き込み6台が炎上、死者4人・重軽傷13人を出す大惨事に至りました。6月21日から7月2日にかけてのわずか12日間でトラックが関与した事故による死者数は15人、負傷者数は35人に達しました。事態を重く見た警察庁は6月25日、全日本トラック協会に対し、法令遵守の指導と運転者の健康管理など厳格な運行管理に関する指導徹底を申し入れ、事故が愛知県内で多発したことから中部運輸局も乗務員指導の徹底を図るよう中部トラック協会に指示しました。
これを受けて全日本トラック協会では、47都道府県トラック協会に対し交通法規の遵守と運行管理の徹底を図るため、会員事業者への周知徹底を要請しました。一方で、事故続発の背景として、トラック運送事業者数の急増と輸送需要の伸び悩みによる競争激化、運賃の下落による無理な運行や過労運転なども指摘されています。また、車線逸脱防止装置や居眠り警報、車間距離警報、被害軽減ブレーキなどASV(先進安全自動車)技術の早期実用化も期待されています。
改正事業法施行、事後チェック強化へ
1990年に施行された貨物自動車運送事業法(トラック事業法)が施行後初めて改正され、2003年4月から施行されました。改正法では、営業区域規制と運賃の事前届出制が廃止され、さらに一段の規制緩和が進められるとともに、適正化事業実施機関の権限強化や罰則強化などの事後チェック体制が強化されました。営業区域の廃止に伴う安全性の担保策としては、運転者の乗務途中の点呼や運行指示書の携行などを新たに義務づけました。
事後チェックとしては、社会保険や労働保険への加入状況を参入時に行政がチェックして適正加入を指導するとともに、監査時や適正化実施機関による巡回指導時にもチェックを行い、改善しない場合は厚生労働省等へ通知する仕組みとしました。監査体制については、地方運輸局等に監査専門の組織を新設し、効率的な監査を推進するとともに、違法性が著しい事業者等への監査の重点化などを進めています。
適正化事業を強化
トラック事業法に基づき、民間の自主的な活動として行われている適正化事業が、事業法改正に対応して強化されました。適正化事業実施機関として、全日本トラック協会と地方トラック協会が指定されていますが、その運営の中立性、透明性を確保するため、中央の貨物自動車運送適正化事業対策協議会の委員に新たにマスコミ、荷主、一般消費者を加えて拡充したほか、地方実施機関においても学識経験者、マスコミ関係者、荷主関係者、一般消費者、組合関係者、トラック事業者を委員とする第三者機関として地方実施機関評議委員会を新たに設置し、適正化事業について評議、提言することになりました。
適正化事業については、権限・体制も強化が図られました。地方実施機関が行う苦情処理の解決などのため、事業者に対し資料等の提出を求める権限が付与されたほか、巡回指導の基準強化、巡回頻度の引き上げ、巡回指導員の専任化と増員などが進められています。
安全性評価事業を開始
トラック適正化事業の新たな事業として、2003年度から事業者の安全性を評価して公表する安全性評価事業が実施されています。荷主や消費者がより安全性の高い事業者を選びやすくするとともに、利用者の選択を通じてトラック事業者が安全対策に取り組む意欲をより高めさせることが狙いで、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関である全日本トラック協会は2003年12月18日、第1回目の安全性優良事業所として1,676事業所を認定しました。さらに2004年1月28日には、書類の不備等で評価中止とした事業所について改めて審査を行い、354事業所を追加認定しました。初年度の2003年度は、評価を希望する全国2,778事業所(うち東京都は222事業所)から認定申請があり、(1)安全性に対する法令遵守状況(2)事故・行政処分状況(3)安全性に対する取り組みの積極性――の3項目を点数化して評価し、合計80点以上得た2,030事業所(同155事業所)を安全性優良事業所として認定しました。認定の有効期間は2004年1月1日からの2年間で、認定証が交付されるとともに、認定マークおよび認定ステッカーを「安全性の高い事業所」の証しとして使用できます。
日本経団連も荷主行動指針
日本経団連は2003年10月21日、大型車両の通行制限緩和を機に、企業行動憲章およびその精神に則って、安全運送に関する荷主としての行動指針を策定しました。行動指針では、法令を遵守し、運送事業者に対して過積載や高さ制限違反等の法令違反となるような要求はしないことを明記したほか、運送事業者の選定にあたり、ISO9001基準や安全性優良事業所認定制度などの客観的な基準を積極的に活用するとされています。さらに、法令違反を繰り返す運送事業者に対しては、取引の停止などを含め毅然とした態度で臨むことを明確にし、運送事業者との協力のもと、安全運送に関する定期的な協議・会合の実施、安全パンフレットの配布など、安全運送の確保と啓蒙活動に努めるとしています。日本経団連では、指針の周知徹底を図るため、関係業界団体や他の経済団体の協力を得て広く産業界全般に浸透するよう努めていく方針です。
スピードリミッター装着を義務づけ
国土交通省は2003年9月1日から、大型トラック(車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上)への速度抑制装置(スピードリミッター)の装着義務づけを開始しました。高速道路での制限速度80km/hを遵守させるため、90km/h以上で加速ができないようにする装置で、高速道路での死亡事故の約4分の1を大型トラックが占め、その過半数を占める追突事故の大半が速度超過で走行時に発生していることから、これらの事故を防止するために義務づけたものです。欧州では1994年から車両総重量12トン以上のトラックに対して装着が義務づけられており、2005年1月からは同3.5トン以上のトラックにまで拡大されることになっています。わが国では、1994年排ガス規制(平成6年規制)適合車以降の使用過程車に対しても3年間かけて義務づけられ、新車への買い替え時にリミッター装着車となるものを含めて計約80万台が対象になると予測されています。装着義務づけにより国土交通省では、高速道路の大型トラックによる死亡事故が20~40%低減されると効果を見込んでいます。
一方で、装着義務づけを巡っては自民党などから事故防止効果や物流、経済に与える影響を懸念する声が高まりました。このため同省では、2003年9月22日にスピードリミッター効果・影響評価検討会を設置し、2006年度末までの3年半かけて事故低減効果や交通流に与える影響、物流体系への影響、ドライバーの労働条件に与える影響などを分析していくことになりました。